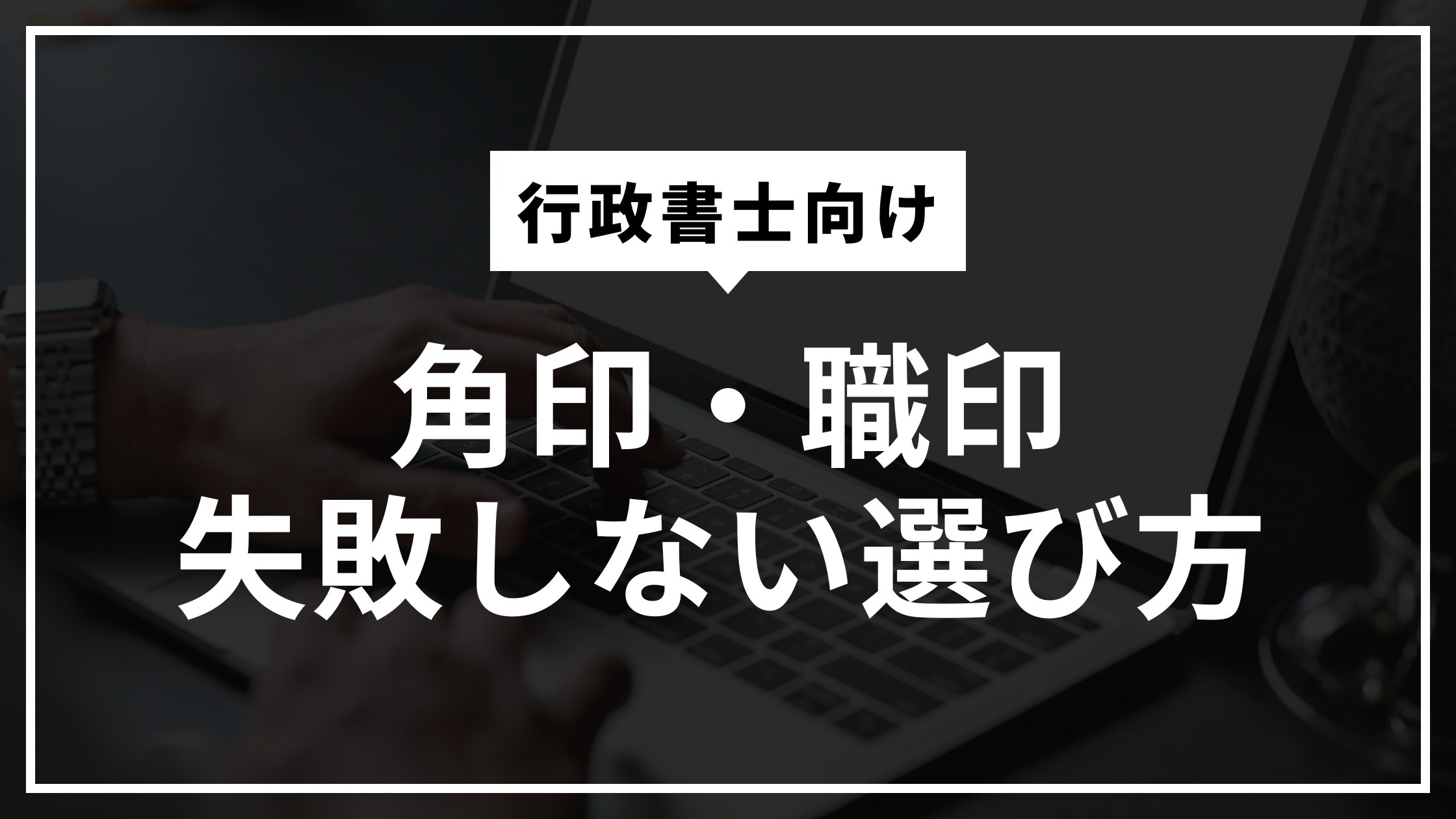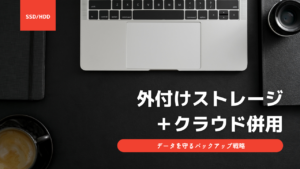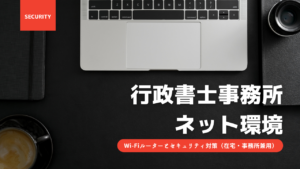目次
この記事のゴール
- 行政書士の角印/職印を“無難に”選ぶ基準
- サイズ・書体・印材の最短解
- 印影サンプルや詳細は、【印鑑本舗】さんを参考
サイズ選び(まず決める)
| 用途 | 無難サイズ | 使いどころ |
|---|---|---|
| 角印(事務所用) | 21mm(大きめは24mm) | 見積書・請求書・納品書、各種証明書の体裁に |
| 職印(個人資格) | 18mm(大きめは21mm) | 案件書類の認印相当、受領印 等 |
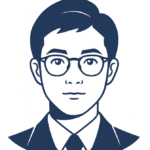 行政書士ツールラボ
行政書士ツールラボ角印21mm+職印18mmの組み合わせがバランス良い。
登録予定の各都道府県の行政書士会によりサイズ指定があります
書体の選び方(印象と可読)
- 古印体:実務での“無難枠”。可読性と重厚感のバランスが良い
- 篆書体:格式高いが可読性は下がる。角印向き
- 楷書体:読みやすいが“軽い”印象。職印に合う場面も
- 角印:21mm × 篆書体
- 職印:18mm × 古印体
印材で決める(耐久×コスパ)
- 柘(ツゲ):コスパ◎。細線に注意/定期メンテで長持ち
- 黒水牛:耐久◎。反りが少なく印影が安定(実務向け)
- チタン(参考):高価だが耐久・メンテ性が高い
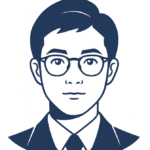
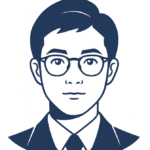
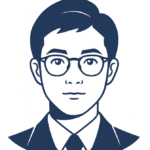
毎日押すなら黒水牛、軽い運用なら柘で十分。
彫刻方式と仕上げ
- 機械彫り:納期速・価格安。一般実務はこれでOK
- 手彫り(手仕上げ):印影の味・偽造耐性。価格・納期は上がる
- 逆打ち/枠有無/アタリ(上下印)などは標準指定で問題なし
管理と予備(失敗防止)
- 予備印を1本用意:紛失・破損・外出時の業務停止を回避
- ケース・朱肉・捺印マットをセットで常備
- 印影のスキャン保存:書類の体裁チェック・押印位置の共有に便利
よくある質問
Q. 角印と職印の書体は統一すべき?
A. 統一不要。角印は篆書体/職印は古印体など用途で分ける例が多い(可読・格式のバランス)。
Q. サイズの組み合わせは?
A. 実務では角印21mm/職印18mmが扱いやすい。角印は21〜24mmが定番帯。
Q. 丸印と角印どちらを作る?
A. 規定がなければ運用で選ぶ。重要書類は丸印/領収等は角印の場面が多い。