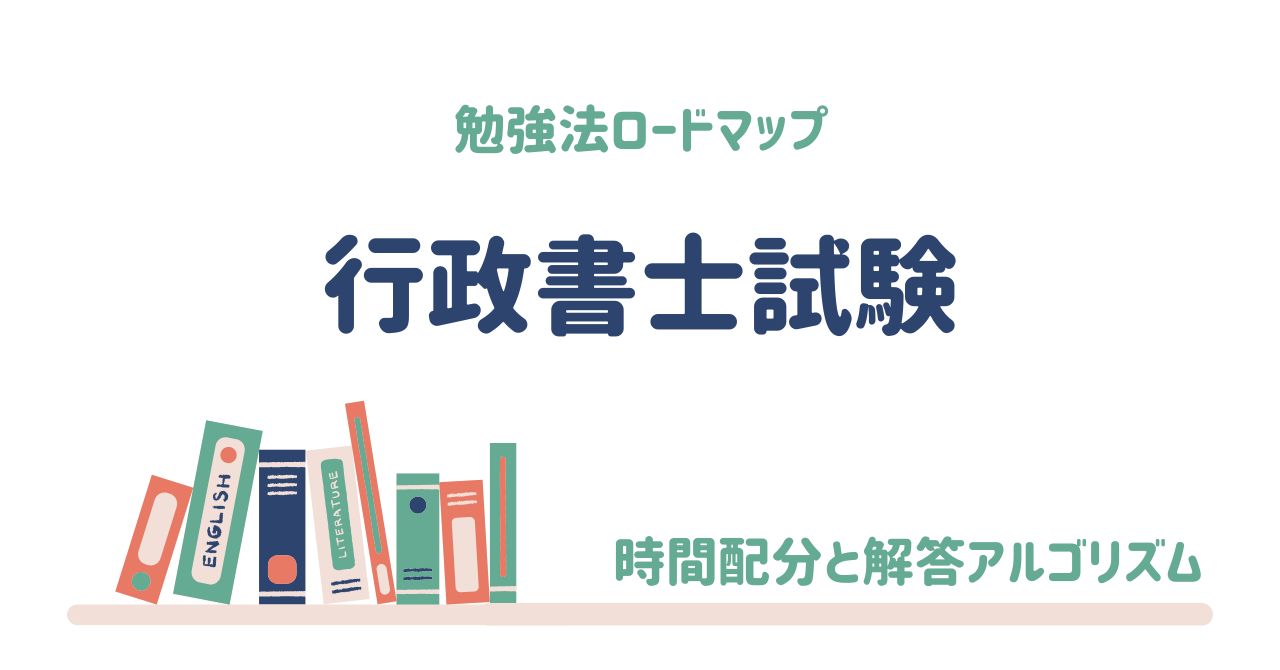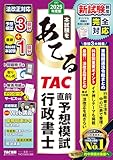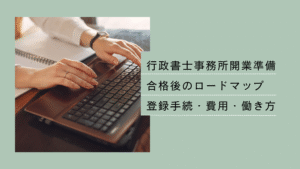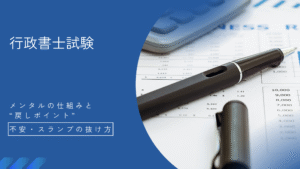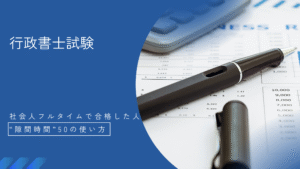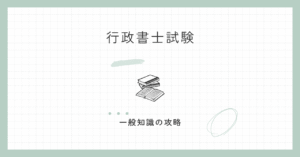結論:順番と手順(アルゴリズム)を“自分用”に固定する
- 回答順番の型をつくる
- 得意先行型(得意分野→記述→苦手)
- 安定走行型(設問順)
- 記述先行型(記述が伸びる人)
- 択一設問のアルゴリズム
- 先読み(設問が何を聞いているか1行で把握)
- 設問分解(論点と要件にチェック)
- 消去法(誤りパターンを先に潰す)
- 1分ルール(迷ったらマーク→後回し)
- 記述設問のアルゴリズム
- 配点を取り切る2ステップ(骨格作りと要件から結論へ)
- 記述のテンプレを意識
- 字数配分の目安を決めておく
- NGを防ぐチェック
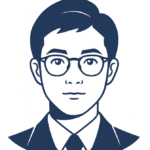 行政書士
行政書士“完璧な1問”より“7割の取り切り”が大切!
ブロック2|時間配分のモデル(模試で“自分版”に調整)
A. 得意先行型(得意分野→記述→苦手)
| 得意な択一(例:基法・憲法・行政法) | 55分 | 1分ルールで滞留回避。確信度◎だけ先に確保 |
| 記述 | 25分 | 骨子→要件→当てはめの順で先に骨を置く |
| 多肢選択 | 15分 | 判別できる空欄から埋め、分からない箇所は一旦飛ばす |
| 苦手な択一(例:民法・商法) | 45分 | 迷いは1分でマーク、後半の時間配分に応じて見直し |
| 基礎法学・一般知識 | 30分 | 知っているものから素早く回収 |
| 見直し | 10分 | マークずれ・計算・記述の日本語だけ |
B. 安定走行型(設問順)
| 択一 | 95分 | 1分ルールでテンポ維持 |
| 多肢選択式 | 15分 | 判別できる空欄から埋め、分からない箇所は一旦飛ばす |
| 記述 | 25分 | 骨子→要件→当てはめで構成先行 |
| 基礎法学・一般知識 | 35分 | 知っているものから即回収 |
| 見直し | 10分 | マークずれ・計算・記述の日本語だけ |
C. 記述先行型(記述が伸びる人)
| 記述 | 30分 | 骨子→要件→当てはめ、序盤の思考鮮度を最大活用 |
| 択一 | 95分 | 1分ルールでテンポ維持 |
| 多肢選択式 | 15分 | 判別できる空欄から埋め、分からない箇所は一旦飛ばす |
| 基礎法学・一般知識 | 30分 | 知っているものから即回収 |
| 見直し | 10分 | マークずれ・計算・記述の日本語だけ |
モデルは叩き台。模試で「どこが詰まったか」を記録し、±5分単位で配分を動かして完成させます。
模試で試行錯誤し、自分の型をつくること。
解答アルゴリズム
択一の解答アルゴリズム
0)見出し先読み(2–3秒)
設問が「定義・要件・効果・判例基準」のどれかを即判定。迷ったら後回しマーク△だけ付ける。
1)設問分解(5–10秒)
問われている要素を最少語でメモ
例)「処分性/不利益処分/聴聞 or 弁明/除外要件」。
2)正解候補の“核”を先に作る(10秒)
「絶対に入る語」を1〜2個だけ確定(条文番号・キーワード)。
例)不利益処分→聴聞/弁明、取消要件→違法+重大性 等。
3)消去法(30–40秒)
誤りパターンを機械的に潰す。
断定過多:「常に」「一切」「必ず」は要注意
逆向き:趣旨・目的を逆にした肢
混ぜ技:正しい文×1+誤り×1の抱き合わせ
数字トラップ:期限・割合・日数の入替
4)1分ルール(上限60秒)
確信◎が無ければ△マークでスキップ。点の薄い1問より、次の1問で確実2点。
5)見直しで回収(試験終盤10分)
△だけ再判定。初回の直感と矛盾しないか、選んだ肢の根拠語が本文にあるかを確認。
マーク運用(答案用紙の余白に)
◎=即答(根拠明確)/○=多分正解/△=後回し/×=読み間違い注意
→ 見直しは△→○の順に触れる。◎は触らない(変更ミス防止)。
記述の解答アルゴリズム“骨子テンプレ”で時短
配点を取り切る2ステップ
A:骨子を20〜40秒で置く
B:要件→当てはめ→結論で肉付け
骨格のテンプレ
論点提示:何の問題か一言(例:処分性の有無/債務不履行の要件)
要件列挙:A・B・C(キーワードだけ。条文番号があれば添える)
当てはめ:設問事実をA/B/Cに対応づけ(因果語:よって/したがって)
結論:端的に(肯定/否定+理由語1つ)
- 字数配分の目安(1問あたり)
- 骨子 2行(10–15秒)
- 要件 3〜4行
- 当てはめ 3〜5行
- 結論 1行
→ 長文は減点リスク。要件語の脱落防止>文章美。
- NGを防ぐチェック(最後の30秒)
- 主語・述語のねじれなし
- 条文や要件語が最低1つ入っている
- 結論が**設問要求(可否・該当性)**に答えている
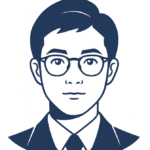
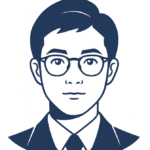
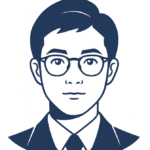
長文は減点リスクであり、差をつけられる得点源。
まず要件語を落とさないことが最優先。
模試で時間配分の戦略建て
- Before(開始前2分):配分を答案用紙にメモ
- メモの例(本番の時間帯も想定)
択一 95分(14:35)
多肢 15分(14:50)
記述 25分(15:15)
一般 35分(15:50)
見直 10分(16:00)
- メモの例(本番の時間帯も想定)
- During
- 各セクションの開始・終了時刻を余白に書く
⇒時間に余裕か遅滞かを常に把握する - 迷いは△マーク。
⇒見直し時間に確認する
- 各セクションの開始・終了時刻を余白に書く
- After(自己採点後)
- 滞留した問題を特定(憲法Q3、民法Q7など)
- 配分を±5分で再設計(例:民法+5、記述-5)
- 1分ルール違反数と見直し実働分を記録(見直しが5分未満ならどこかで滞留)
- KPI:見直し10分確保率100%/1分ルール違反0~2問。
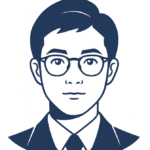
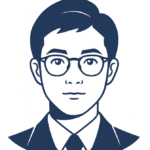
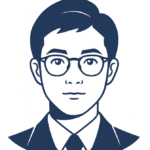
3時間は長丁場。後半の集中切れが当たり前だと想定し、試験期間中にも戦略を立て直す。模試で時間配分の訓練をしておきましょう!
当日の運用チェックリスト
- 開始前
- 時計や文具の位置
- 時間配分メモ
- 水分・ブドウ糖(小)
- 択一:確信◎→先回収、迷いは1分で△。語尾・断定語に注意。
- 記述:骨子→要件→当てはめ。空欄回避(最低限の結論は必ず書く)。
- 見直し(10分):
- マークずれ/計算/記述の主語・述語のズレ
- △だけ素早く再判定(新たな迷いは最初の直感を信じる)
- 心拍の管理:45–60分おきに10秒だけ視線を外す(ミクロ休憩)。
焦りを感じたら深呼吸3回で常に平常心を意識する。